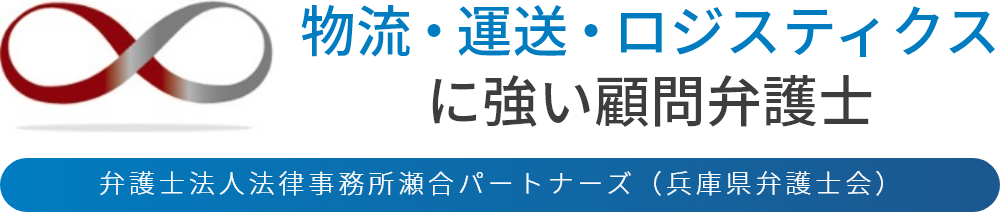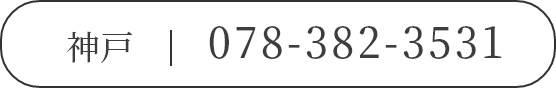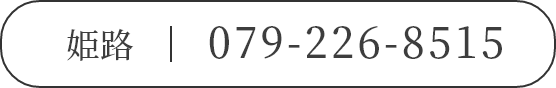1 はじめに
近年、大手通販サイトの躍進等により、延べ面積が5万㎡以上の大規模な倉庫が、急増しています。延べ面積が5万㎡以上の大規模な倉庫数は、平成13年からの15年間で約6倍にもなっているといったデータもあります。そのため、一カ所の倉庫に多くの荷物が集積されるほか、産業車両や重機の使用も要するため、火災事故をはじめとする事故による損害リスクが増大しているといえます。近年では、事務用品通販大手企業が、物流倉庫で発生した火災をめぐり、段ボールを回収していた紙加工業者に対し損害賠償を求めていた裁判で、東京高裁が、約94億円という巨額の賠償金の支払いを命じました。
では、実際に倉庫において火災事故が生じたとき、倉庫業者は荷主等に対し、どのような法的責任を負うのでしょうか。以下、この点について解説していきたいと思います。
2 民法上の損害賠償責任
(1) 債務不履行と不法行為
民法上、倉庫業者に損害賠償を求める構成としては、債務不履行構成(民法415条)と不法行為構成(民法709条)が考えられます。前者は、契約関係にある当事者間で、債務が不履行になった場合に発生するものです。これに対して、後者は、契約関係にない当事者間でも成立するものです。いずれも、違反行為者に過失等があることがその要件となります。
(2) 失火責任法と適用範囲
もっとも、火災による損害賠償については、失火責任法上、「民法709条の規定は失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」という規定が定められており、失火者が不法行為責任を負う場合を「重過失」に限定し、行為者の責任を軽減しています。
このように、行為者の責任が軽減されている趣旨は、日本の家屋には木造家屋が多く、火災が発生すると燃え広がって、莫大な損害が生じることが多いことと、失火の際には加害者自身も焼け出されている場合が多いことにかんがみ、加害者の賠償責任が発生する場合を限定することにあります。
なお、ここでいう「重過失」とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指す」とされています(最高裁昭和32年7月9日判決)。
ただし、債務不履行責任に対しては、失火責任法の適用は及ばないとされています。そのため、寄託契約の当事者である寄託者(荷主)は、受託者である倉庫業者に対して、不法行為責任ではなく、債務不履行責任に基づいて、損害賠償を請求していくことになります。
(3)約款による軽過失免責
この点、倉庫営業者(他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者)の場合は、受寄物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しないかぎりその滅失・損傷につき損害賠償の責を負う旨規定されています(商法610条)。
しかしながら、企業である寄託者は取引を熟知している等の理由から、標準トランクルームサービス約款(同約款では上記と同趣旨を定めています)を除き、他の約款では例外なく、損害が倉庫営業者またはその使用人の故意または重過失により生じたことを寄託者側が証明しないかぎり倉庫営業者は賠償の責めを負わない旨が定められています。
そのため、企業と倉庫営業者間の寄託契約の場合、念のため約款を確認したうえで、倉庫営業者の立場であれば、寄託物の滅失・毀損について故意または重過失がないこと(寄託企業の立場であれば、寄託物の滅失・毀損について故意または重過失があること)を主張・立証していくようにする必要があります。
(4)重過失
では、具体的にどのような場合に重過失が認定されるのでしょうか。以下、倉庫業者に重過失が認められた事例をご紹介しておきます。いずれも商慣習上、倉庫業者が当然になすべき義務を果たさなかったことを理由に重過失が認定されているものと考えられます。
➀東京地裁昭和41年3月28日判決
倉庫業者が、高価な受寄物について下請業者に作業させたところ、一部盗取にあったことから、倉庫業者の保管義務違反の有無が争点の一つとなった事案です。
「倉庫業者は・・・高価な受寄物のスクラップ化のため、これを下請させるような場合には盗難事故が生じないようにその作業員の監視を強化する等特段の予防処置を講ずべき義務がある。・・・被告は、・・・保税工場のうち公道に面した側に高さ約六尺のトタン塀をつくり、夜間は湘南ワッチマン株式会社に依頼して毎日一名の警備員による警備をさせたのみで、他に特段の措置を講じたことを認めるに足る証拠はない。したがって、被告は右注意義務を怠りそのため本件物件のスクラップ化を下請させた業者の作業員の一部盗取にあったものというべく、前示本件物件の重量不足は、被告の保管上の重大な過失によって生じたものといわなければならない。」
➁東京高裁昭和49年5月9日判決
倉庫業者側の火災保険の過小申告によって、寄託業者が寄託商品について損害を被ったとして、倉庫業者に損害賠償を求めた事案です。
「控訴会社もこの取引例に従い、被控訴人と倉庫寄託契約を締結するに当っては被控訴人を被保険者とする保険契約を締結していたのであるから、控訴会社は右寄託契約上の義務として、受託商品の全価格につき火災保険の申告をすべき義務があるということはいうまでもない・・・。
訴外Z社の係員は、被控訴人買受の商品を控訴会社倉庫に搬入・引渡しをするに当って、商標・品名・数量(ピース)を記載した納品書(単価・金額の記載はない。)を控訴会社従業員に示し、右従業員はこれをもって搬入商品の点検・査収をしたうえ、これに押印して右搬入係員に変換する取扱になっており、しかも、右納品書には誤解を避けるためあえて梱包数は書かず、特定品名毎の数量(ピース)のみが数量蘭に記載されているほか、各梱包の外装には品名・規格等とともに梱包中の数量も表示されていたというのであるから、本件商品の入庫査収に当り、控訴会社従業員Aがこの「数量」の記載・表示を看過して品名・規格と梱包数のみをメモしたものを同従業員Bに手渡し(同女は当時入社後間もなかった)、更にBがそのメモを利用して寄託申込書・入庫報告書等を作成するに際して、被控訴人に対し漫然「単価」のみを電話で問い合わせ、この「単価」に右の梱包数を乗じて受託価格、すなわち保険金額を算定し、火災保険の申告に及んだのは、前記寄託契約上の義務の履行として尽すべき注意義務を著しく怠ったものということができる。」
(5)損害保険
上記のとおり、倉庫営業者は免責の範囲が広いため、受寄物の滅失・損傷につき保険で対応する必要性が大きいといえます。そこで、倉庫業法は、倉荷証券が発行される受寄者については、寄託者の反対の意思表示がないかぎり、倉庫営業者を保険契約者、寄託者である倉荷証券所持人を被保険者とする火災保険を付保することを要求しています(倉庫業法14条)。また、普通倉庫では、約款により、倉荷証券の発行の有無にかかわらず同保険を付保しています。
もっとも、火災保険は寄託者に関するすべての損害を担保するわけではありません。そこで、上記保険で担保されない損害を付保しようとする寄託者は、自己の負担において期間建運送保険契約を締結することをご検討ください。
(6)損害の範囲
また、倉庫において火災事故が生じた場合、損害賠償の対象となる損害として考えられるものとしては、延焼物を含む保管物や物流倉庫自体の滅失・棄損、火災対応に要した費用、廃棄処分費用、代替倉庫にかかった費用、倉庫の機能不全による販売機会の喪失、死傷者が生じた場合の人的損害、弁護士費用等が考えられます。滅失・毀損した保管物の時価額が問題となることも珍しくありません。
火災事故の場合、煙や煤、臭気による損害、近隣住民に対する補償等といった火災事故に特有の問題も生じるおそれが高いでしょう。
3 過失相殺
なお、債務不履行責任構成をとるにせよ、不法行為責任構成をとるにせよ、過失相殺が問題となり得ます(民法418条、722条2項)。
債務不履行責任構成においては、債務の不履行の成立それ自体、または債務不履行による損害の発生ないし拡大に関し、債権者に過失があったときには、裁判所は、損害賠償の責任およびその金額を定めるにつき、これを斟酌します(民法418条)。
また、不法行為責任構成においては、被害者に過失があったとき、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができます(民法722条2項)。
自分に生じる損害を回避したり、減少させたりするための行動が債権者又は被害者に期待できるときには、そうした行動をとらなかったことによる不利益を債権者又は被害者に負担させるのが公平にかなうと考えられるからです。
ですので、寄託者である荷主が、倉庫業者に保管物を寄託する際、保管方法について不適切な指示をして損害が拡大した等といった荷主の落ち度と考えられる事情があれば、過失相殺される結果、損害金額が下がる可能性があります。
4 保険金と損益相殺・保険者代位
また、債務不履行構成をとるにせよ、不法行為構成をとるにせよ、債権者が損害を被るとともに、同一の原因によって利益を受けた場合に、損害と利益との間に同質性・相互補完性がある限り、その利益の額は賠償されるべき損害額から控除されます。これを損益相殺といいます。損害と利益の間に同質性・相互補完性が認められるかが重要となります。
この点、寄託者である荷主が、火災事故によって火災保険金を受け取ったとしても、損害保険金はすでに支払った保険料の対価として給付されるものなので、損害と利益の間に同質性は認められず、損益相殺の対象とはなりません。
ただ、損害保険には、一般的に代位が認められていますので、火災保険金を支払った保険会社は、その限りにおいて、荷主の倉庫業者に対する損害賠償金を取得します(保険者代位・商法622条)。
その結果、寄託者である荷主が請求できる損害賠償金は減るおそれがあると考えられます。
なお、火災の原因が法令違反(建築基準法違反等)の事実に起因し、かつそれと相当因果関係がある場合、火災保険約款の免責に該当し、保険金支払い対象外となるおそれがありますので、ご注意ください。
5 責任の短期消滅時効
もう一点、注意しないといけないのは、消滅時効です。寄託契約に特有の短期消滅時効が定められており、具体的には、寄託物の滅失・損傷による倉庫営業者の責任は、悪意がない限り、出庫の日(寄託物全部滅失の場合には、倉庫営業者が倉荷証券所持人または寄託者に対し滅失の通知を発した日)から1年を経過したときは、時効により消滅しますので、倉庫寄託契約の当事者は、この点に留意する必要があります。
6 まとめ
以上のとおり、倉庫において火災事故が生じたときに、倉庫業者が荷主等に対し、負う
べき法的責任や火災保険金との関係について、解説させていただきました。倉庫の大規模化により、火災が生じた場合の損害額も大きくなり、法的責任も複雑になるおそれがあります。倉庫寄託契約に関する法的問題にお悩みの企業様は、この分野に詳しい弁護士に是非ご相談ください。
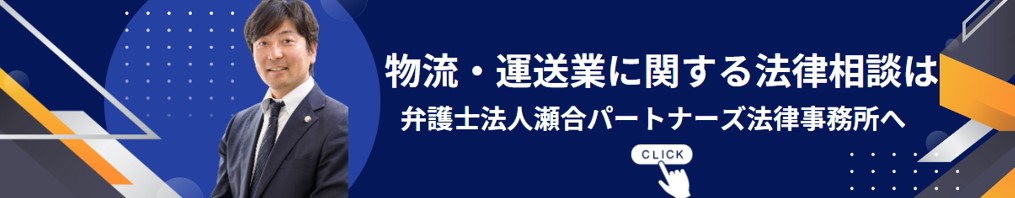
Last Updated on 2024年4月15日 by segou-partners-logistic