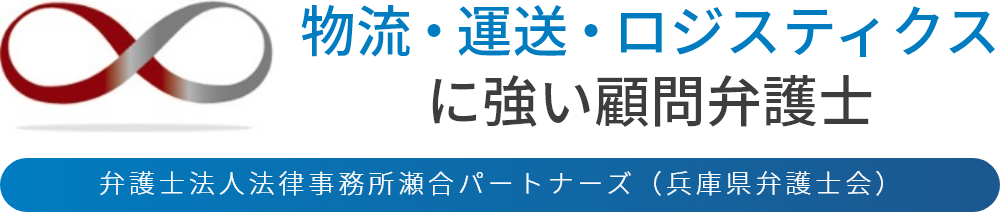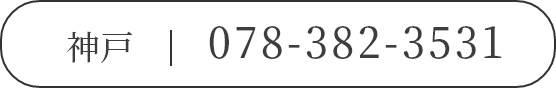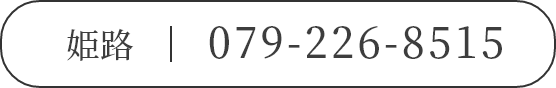1 初めに
2025年6月4日、国会で「貨物自動車運送事業法」の改正法が可決・成立しました。この改正は、トラックドライバーの労働時間規制(いわゆる「2024年問題」)に端を発した、物流業界の構造的課題への抜本的な対応策の一環です。特に、ドライバーの過重労働・低賃金構造、輸送体制の不透明さ、多重下請による輸送品質の劣化など、長年指摘されてきた問題に正面から向き合う法改正となりました。
この記事では、今回の改正の背景と目的、改正内容の主要ポイント、そして運送事業者が取るべき実務的対応、今後のスケジュールについてわかりやすく解説します。
2 法改正の背景と目的
流業界では長年にわたり、「長時間労働」と「低賃金」という問題が指摘されてきました。とりわけトラックドライバーについては、荷待ち・荷役作業の長時間化、過密な運行スケジュールによる安全面のリスク、さらには不透明な取引構造によって不当に抑えられる運賃など、深刻な課題が山積みしていました。
2024年4月からは、働き方改革関連法によりドライバーにも時間外労働の上限(年960時間)が適用され、輸送能力の制限が現実のものとなりました。これが物流の「2024年問題」と呼ばれる事態です。
今回の法改正は、こうした背景を受け成立したものであり、2024年問題に対応し、物流の危機を乗り越えるための一手として注目されています。
3 主な改正ポイントの整理
今回の改正には、以下のような物流業界に大きな影響を及ぼすポイントが盛り込まれています。
⑴ 実運送体制管理簿の作成義務の拡大
元請事業者は、貨物の輸送に実際に関与した運送事業者(実運送事業者)を明示する「実運送体制管理簿」を作成・保管する義務を負います。従来は一部の事業者にのみ求められていましたが、今回の改正により、義務の対象が拡大される見通しです。
この制度により、輸送体制の「見える化」が進み、行政による実態把握や監査も可能となります。不透明な多重下請構造を是正することが主な目的です。
⑵ 下請は2次請以内に制限(努力義務化)
荷主から引き受けた貨物の輸送について、これまでは、元請→1次請→2次請→3次請…といった多重下請構造が常態化していましたが、今回の改正により、2次請までに抑えることが努力義務として制度化されました。強制力はないものの、行政指導や業界内のガイドライン整備を通じて、事実上の「多重下請の抑制」が強く求められることになります。
3次請や4次請となると、運送責任の所在が曖昧になりやすく、事故発生時の対応も困難になります。加えて、中間マージンが多層に重なり、現場のドライバーに適正な対価が支払われない構造も温存されていました。今回の改正はこうした悪循環を断ち切る契機とされます。
⑶ 「適正原価」の告示制度
国土交通省が人件費や燃料費等を反映した「適正原価」を告示し、これを下回る運賃設定は禁止されることになりました。これにより、価格交渉の土台が明確化され、荷主との交渉がしやすくなると期待されています。
過去の調査でも、運送事業者がコストを下回る運賃で請け負わざるを得ない状況が多く確認されており、本制度は、そうした「買いたたき」防止策の一環です。
⑷ 事業許可の「終身制」から「5年更新制」へ
これまでは一度事業許可を取得すれば原則として無期限で有効でしたが、今後は5年ごとに更新が必要になります。更新の際には、運行管理体制・安全確保・法令順守の状況が審査されるため、継続的なコンプライアンス体制の整備が求められます。
この制度は、業界内の「不適切事業者」の排除にもつながるとされ、質の高い事業者が生き残る時代へと移行していくことになります。
⑸ 無許可業者への委託の禁止と荷主への罰則
これまで問題視されていた無許可業者(いわゆる「白トラ」)への運送委託について、委託元だけでなく、荷主側にも罰則が課されることとなりました。
これにより、荷主も含めた「適正な輸送体制の選定責任」が強く問われるようになります。物流の安全性と透明性を守るためには、荷主側の意識改革も不可欠です。
⑹ 労働者処遇の適正化・明確化
改正法では、ドライバーの能力や知識に応じて適正な賃金を支払うなど、労働者の処遇確保・改善が法的義務となりました。
労働者の処遇については、許可更新時の審査項目にも含まれる見通しであり、対応が遅れれば、更新が通らないおそれもあるため注意が必要です。
4 実務上の対応
運送事業者にとって、今回の法改正は単なる制度変更ではなく、日々の事業運営に直結する大きな転換点です。今後は、以下のような対応が必要になるでしょう。
・社内体制の整備
実運送体制管理簿の記録・保管に加えて、労働者の処遇改善のため、賃金制度・評価制度の整備が必要になります。
・委託先の見直し
下請が2次請以内に収まるような委託体制への見直し、契約条項の再整備が必要になります。
・許可更新制度への備え
ドライバーの拘束時間を把握・管理するとともに、社内監査を導入するなどしてコンプライアンス強化を図り、許可更新審査に耐えうる体制を作ることが求められます。
・運賃交渉戦略の構築
自社のコスト構造と国土交通省が示す「適正原価」を照合し、その差異を把握しましょう。荷主との運賃交渉の際には、運賃算定の根拠資料を作成することで、荷主と対等な交渉を行うことが可能となります。
5 今後のスケジュール
改正法のうち、制度設計に時間を要することが想定される適正原価の告示、許可更新制度、労働者処遇の確保などは公布日から3年以内の施行が予定されています。
他方で、実運送体制管理簿の作成義務拡大や、下請の制限、無許可業者への委託禁止などは公布日から1年以内に施行される見通しです。
6 終わりに
2025年の貨物自動車運送事業法改正は、物流業界にとって「制度の大転換」ともいえる内容です。これにより、輸送品質・ドライバーの待遇・運送事業者の健全性を総合的に底上げする方向性が明確になりました。
今後、運送事業者には、単なる制度対応ではなく、「持続可能な物流」の実現に向けた中長期的な視点での取り組みが求められます。社内のガバナンス体制、荷主との連携、そして法令順守の意識が問われる時代です。
ぜひ、早期の情報収集と社内準備を進め、制度変更の波を成長の機会と捉えて対応していくことをお勧めします。
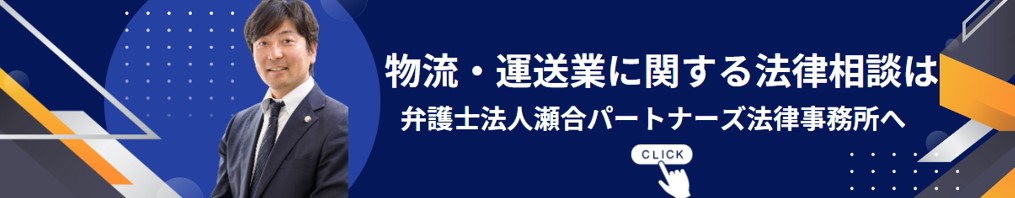
Last Updated on 2025年8月4日 by segou-partners-logistic