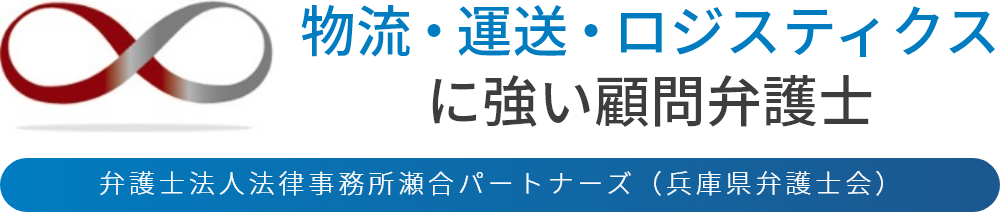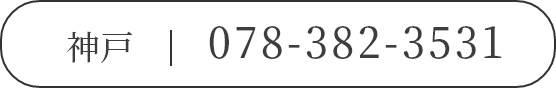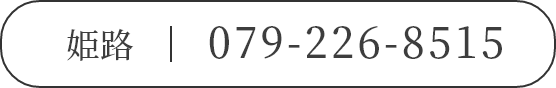1 はじめに
日本の経済活動を支える大動脈である運送業。しかしその裏側では、長時間労働や賃金未払いといった労働基準法違反が後を絶たず、それが重大な事故の引き金となるケースも少なくありません。
特に「2024年問題」に直面する今、運送事業者が法令を遵守し、ドライバーの安全と健康を守ることは、企業の存続そのものを左右する喫緊の課題となっています。
本記事では、運送業界における労基法違反の現状から、経営者や運行管理者が負うべき法的責任について解説します。
2 運送業界の労基法違反の現状と主な違反事例6選
運送業界では、過酷な運転スケジュールや、荷主からの無理な依頼に対応するうちに拘束時間が延びること等により、労基法に違反した事例が散見されます。
主な違反事例は以下の通りです。
⑴ 違法な長時間労働
時間外労働の上限規制(労働基準法36条)を超えた労働や、トラック運転者向けの「改善基準告示」で定められた拘束時間(1日原則13時間、1ヶ月原則284時間など)の超過が常態化しているケース。
⑵ 割増賃金の未払い
時間外、休日、深夜労働に対する正当な割増賃金が支払われていない(労基法37条1項違反)ケース。
⑶ 休日の不確保
労基法35条で定められた最低限の休日(週1回または4週4日)を与えず、ドライバーに連続勤務を強いるケース。
⑷ 不適切な休憩時間の管理
荷物の積み下ろしを待つ「手待ち時間」を労働時間と見なさず、休憩として処理してしまうケース。
⑸ 年次有給休暇の未取得
2019年から労基法39条7項で義務化された、年5日の年休取得をさせられていないケース。
⑹ 健康診断の未実施
深夜業に従事するドライバーに対し、労働安全規則45条で義務付けられている特定業務従事者健康診断(年2回)を実施していないケース。
3 労働時間・休日・賃金管理の落とし穴
運送業の労務管理には、特有の複雑さと注意すべき「落とし穴」が存在します。
⑴ 労働時間管理の要「改善基準告示」
運送業の労務管理を語る上で欠かせないのが、厚生労働大臣が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)です。これは労基法を補完するルールであり、拘束時間の上限や休息期間の確保について具体的に定めています。
- 1年の拘束時間:原則3,300時間以内(最大3,516時間)
- 1ヶ月の拘束時間:原則284時間以内(最大310時間)
- 1日の休息期間:継続11時間を基本とし、最低でも9時間を確保
⑵ 賃金管理の盲点「固定残業代」と「歩合給」
賃金トラブルで特に多いのが「固定残業代(みなし残業代)」制度の誤用です。この制度を有効とするには、①所定内の賃金部分と固定残業代部分とが判別できること(区分性の要件)、②時間外労働の対価として支払うことの合意がなされていること(対価性の要件)が必要です。
4 経営者・運行管理者の安全配慮義務と刑事・民事責任
ドライバーが過労により事故を起こした場合、その責任はドライバー個人だけにとどまりません。経営者や運行管理者にも重い法的責任が問われます。
⑴ 安全配慮義務とは
労働契約法第5条には、使用者(会社)が労働者の生命や身体の安全を確保しながら働けるように配慮する「安全配慮義務」が定められています。運送業においては、過労運転にならないよう労働時間を適切に管理し、十分な休息を与えること、健康状態を把握すること、車両を安全に整備することなどが、この義務の具体的な内容です。
⑵ 民事責任
安全配慮義務を怠り、その結果として事故が発生した場合、会社は、事故の被害者から損害賠償を請求されるだけでなく、被災したドライバーやその遺族からも、安全配慮義務違反を理由に多額の損害賠償を請求される可能性があります。
⑶ 刑事責任
労働安全衛生法は、事業者に対し労働災害防止措置を義務づけています。労働災害の発生の有無を問わず、これを怠ると刑事責任が課せられます。また、業務上労働者の生命、身体、健康に対する危険防止の注意業務を怠って、労働者を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪(刑法第 211 条)が問われることになります。
5 事故防止のための現場管理・休養体制の実務策
法的リスクを回避し、ドライバーの安全を守るためには、実務に根差した具体的な対策が不可欠です。
デジタコ(デジタルタコグラフ)やGPS等のデジタルツールの活用、AIなどを活用した配車支援システムの導入、点呼の強化(アルコールチェックはもちろん、睡眠時間や疲労度合いの確認、健康状態に関する対話を丁寧に行うこと)、勤務終了から次の始業まで、最低9時間、基本11時間の休息期間を確実に確保する運行計画を立てること等が必要になるでしょう。
6 監督強化の流れと今後の法的リスク
ここ数年、安全対策強化のために運送業者に対する行政による監督は一層強化されています。また、未払い残業代請求や過労死・過労事故に関する高額な損害賠償請求も増加しています。
7 まとめ
運送業における労基法遵守と安全配慮義務の徹底は、もはや単なるコンプライアンスの問題ではありません。それは、ドライバーの命を守り、社会インフラとしての信頼を維持し、そして何よりも自社の事業を未来へと繋ぐための最重要経営課題です。
「2024年問題」は、運送業界に大きな変革を迫る厳しい試練ですが、同時に、旧来の長時間労働に依存した経営モデルから脱却し、生産性の高い、持続可能な事業構造へと転換する絶好の機会でもあります。
労務管理を見直そうとお考えの運送事業者は、運送業に詳しい弁護士にご相談ください。
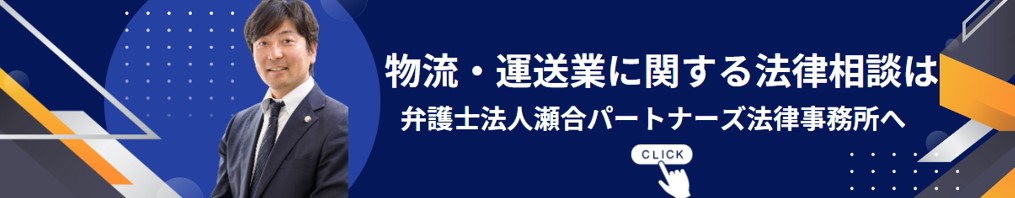
Last Updated on 2025年8月4日 by segou-partners-logistic