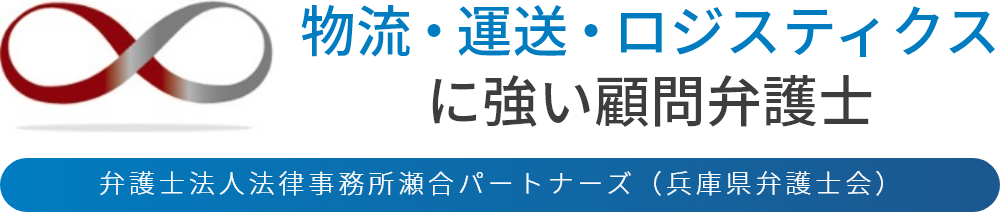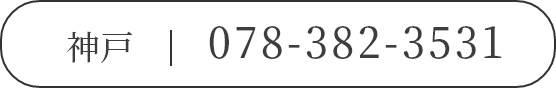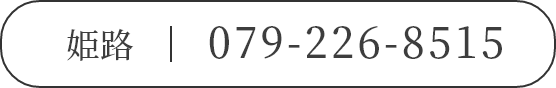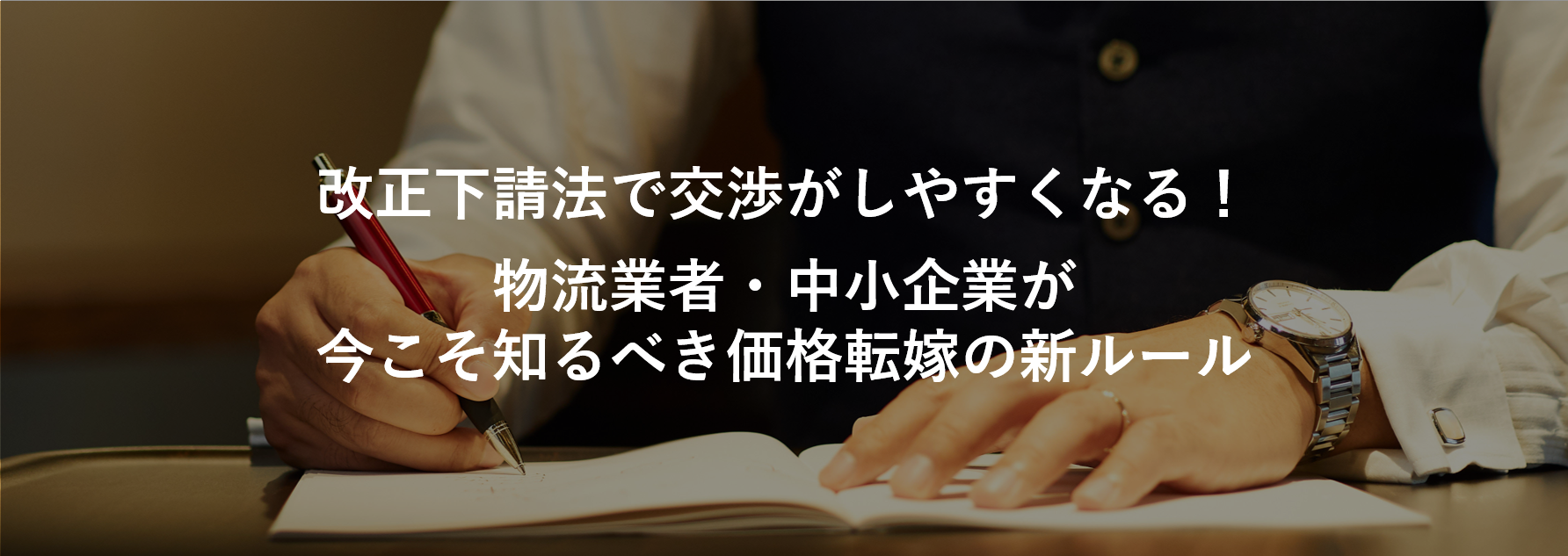1.受注側にとって追い風となる法改正
燃料費の高騰や人件費の高騰が起きても、取引の立場の弱い受注者は、商慣習上、価格交渉すらできず、負担を負う構造となっており、健全な取引環境が整備されているとは言い難い状況でした。
下請法の改正により、価格転嫁を阻害し、受注者に負担を押し付ける商慣習を一掃することで、取引の適正化が図られることとなります。
2.改正下請法のポイント
(1)荷主からの委託も下請法対象に
発荷主から元請運送事業者への委託は、本法の対象外で、独占禁止法の物流特殊指定で対応がされてきましたが、新たに現行の物品の運送の再委託に加えて物品の運送の委託が規制対象に追加されることとなりました。
(2)不当な無償作業の禁止
立場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主・物流事業者間の問題が顕在化していましたが、改正下請法の下では、2⑴で述べたように、荷主からの委託も下請法の対象とすることで、不当な無償作業が禁止されました。
(3)価格交渉の義務化・協議記録の重要性
改正下請法では、価格決定のプロセスが重視されています。中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、委託事業者が必要な説明を行わないことを禁止し、価格交渉を義務付けています。また、価格決定のプロセスが重視されることに伴い、協議の記録を残しておくことが重要となってきます。
3.実務上よくある問題とどう変わるか
(1)荷待ち時間、燃料費上昇の未反映
従来、荷待ち時間が長時間にわたっても料金に反映されないという荷主・物流事業者間の力関係を原因とした問題が顕在化していました。さらに、燃料費が上昇した場合でも、価格が据え置かれ、取引の立場の弱い受注者(中小企業・小規模事業者)が負担を負う構造でした。
改正下請法では、発荷主が運送事業者に対して、物品の運送を委託する取引を本法の適用対象とし、長時間の荷待ち問題に対応するとともに、下請事業者からの価格協議の申し入れに応じないことを禁止しました。
(2)手形払い・一方的な単価決定などの見直し
物流業界では、支払手段として手形等を用いることにより、発注者が受注者に資金繰りに係る負担を求める商慣習が続いていたり、単価が一方的に決定されていました。
今後は、中小受託事業者保護のために、支払手段として手形払いが認められないこととなり、また単価の一方的な決定も禁止されます。
4.中小企業・物流事業者のとるべき行動
(1)契約見直しのタイミング
荷主との間で、曖昧な合意、慣習に基づいて荷役や荷待ちが行われていないか、約束手形を用いて支払いが行われていないかなど、令和8年1月1日に予定されている改正下請法の施行日までに、早めに見直しを進めていきましょう。
(2)価格交渉の「正当性」をどう示すか
改正下請法は、代金に関する協議に応じない、必要な説明・情報提供を行わないことによる一方的な代金額の決定などの協議を適切に行わない代金額の決定を禁止するなど、価格交渉のプロセスを重視していることからすると、価格交渉の記録(メール、議事録、提案書など)を残すことが重要となってきます。
5.弁護士を活用する方法
法律の専門家である弁護士が助言することで、貴社に法的に理論武装していただいたうえで、価格交渉に臨んでいただくことが可能になるなど、様々な場面でお力になれると思います。
不当に弱い立場に立たされることなく、適切に取引を行うためにも、この分野に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
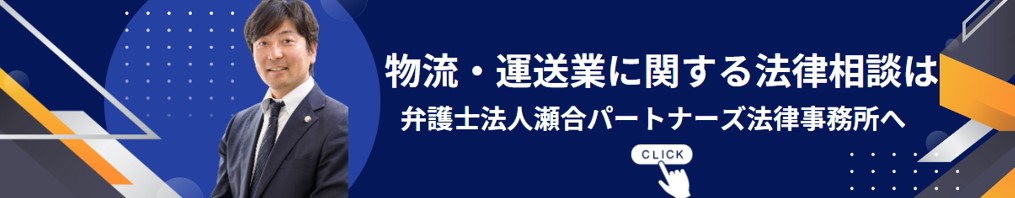
Last Updated on 2025年8月4日 by segou-partners-logistic