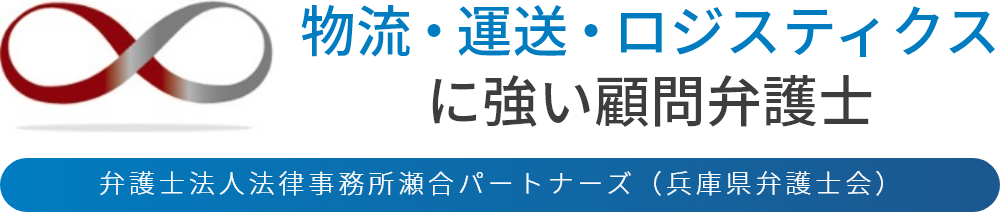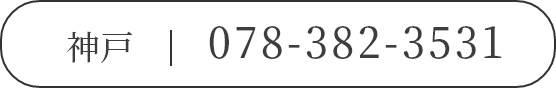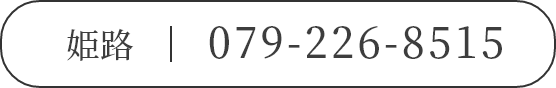1.2024年問題と下請法改正の動き
「働き方改革関連法」に伴う時間外労働の上限規制は、2019年4月から施行されていますが、自動車の運転業務などの一定の事業については、5年間適用が猶予されていました。しかしながら、2024年4月、この5年間の猶予期間が終了し、自動車の運転業務についても年間960時間の上限規制が適用されました(いわゆる「2024年問題」)。
物流業界では、トラック運転手の担い手不足が問題視される中、「2024年問題」に直面し、我が国の物流が停滞することが懸念されています。
このような動きの中、2024年5月、公正取引委員会は、荷主から運送事業主に対して妥当な対価が支払われるようにする目的で、下請法の改正に乗り出しました。具体的には、荷主と運送事業主の取引が下請法の対象となり、荷主の違反行為に対する排除措置命令が機動的に行えるようになります。
以下では、下請法の具体的な改正内容、荷主の禁止行為などについて、具体的に解説していきます。
2.下請法の適用範囲拡大
(1) 下請法とは
下請法は、昭和31年、独占禁止法による優越的地位の濫用規制を補完する法律として制定されました。
独占禁止法においては、行為者が優越的地位にあること、対象行為が公正な競争を阻害するおそれがあることが適用要件とされています。しかしながら、優越的地位があるか否かといった事実認定には時間がかかり、下請事業者が十分に保護できないことから、客観的な基準によって簡易迅速に優越的地位の有無が判断できるよう、下請法が制定されました。
具体的には、資本金条件、委託内容という明確な基準により、優越的地位にある「親事業者」にあたるかが判断されます。
① 製造委託、修理委託、政令で定める情報成果物作成委託、役務提供委託の場合
| 親事業主 | 下請事業主 |
| 資本金3億円超 | 資本金3億円以下又は個人 |
| 資本金3億円以下又は個人 | 資本金1千万円以下又は個人 |
② それ以外の情報成果物作成委託、役務提供委託の場合
| 親事業主 | 下請事業主 |
| 資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下又は個人 |
| 資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下又は個人 |
(2) 下請法改正以前の問題点
下請法は、上記のとおり、「製造、修理、情報成果物作成、役務提供」の委託取引において適用されますが、「役務提供委託」は、「事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」(下請法第2条4項)と定義されており、運送事業を本業としない荷主と運送業者間の取引は「役務提供委託」に該当せず、下請法の適用外となっていました。
そのため、荷主と運送事業主との間の取引は、独占禁止法の物流特殊指定が適用されていましたが、優越的地位の濫用における判断基準の一部が争点となり、違反行為に対する措置を命じる排除措置命令を出すまでに時間を要していました。
(3) 下請法改正による「特定運送委託」の追加
以上の問題点を踏まえ、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が令和7年3月11日に閣議決定され、同年4月24日、衆議院で可決されました。同改正法は、衆議院の決議により、「令和8年1月1日」に施行されることが予定されています(参議院の審議により修正される可能性があります)。
下請法の改正により、荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引が「特定運送委託」として新たに追加され、独占禁止法ではなく、下請法が適用されるようになります。その結果、荷主の違反行為に対して、迅速に原状回復等の措置を命じることができます(改正下請法2条5項、6項)。
3.荷主が注意すべき禁止行為
荷主と運送事業主との間に下請法が適用されるため、荷主は以下の行為をすることが禁止されます(下請法第5条)。たとえ、運送事業主の了解を得ていた場合や、荷主に違法性の認識がない場合であっても、下請法違反となるので注意が必要です。
(1) 受領拒否
(2) 代金の支払遅延・手形払等の給付
(3) 代金の減額
(4) 返品
(5) 買いたたき
代金額を決定するときに、発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して、通常支払われる対価に比べて著しく低い額
を不当に定めることは「買いたたき」に該当し、下請法違反となります。
(6) 購入・利用強制
(7) 報復措置
運送事業者が、荷主の不公正な行為を公正取引委員会、中小企業庁、事業を所管する大臣に知らせたことを理由として、運送事業主に対して、
取引数量の削減・取引停止等の不利益な取り扱いをすることが禁止されます。
(8) 有償支給原材料等の対価の早期決済
(9) 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
(10) 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
(11) 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
4.法改正後の取引における留意点
上述の荷主の禁止行為のうち、以下の2つの行為については法改正がされるため、注意が必要です。
(1) 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
荷主が、コスト上昇に見合わない価格を一方的に決めることが問題視され、荷主と運送事業主の対等な価格交渉を確保する目的で、新設される条項です(改正下請法第5条2項4号)。
運送事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じない場合や、荷主が必要な説明を行わない場合など、一方的に代金を決定して、運送事業主の利益を不当に害する行為が禁止されます。
(2) 手形払等の禁止
荷主が支払手段として手形を用いることにより、運送事業主に資金繰りの負担を求めることが問題視されていました。
そのため、荷主の支払手段として、手形払を認めないこととし、電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに相当する金銭を得ることが困難であるものを使用することは禁止されます(改正下請法第5条1項2号)。
5.違反した場合のリスク
(1) 立入検査
公正取引委員会、中小企業庁は、取引の公正を確認するため、荷主、運送事業主に対する書面調査を毎年実施します。また、必要に応じて、荷主の保存している取引記録の調査や立入検査が実施されます。
(2) 勧告・公表
公正取引委員会は、荷主が下請法に違反した場合、それを取りやめて原状回復させること(減額された対価の支払い等)を求めるとともに、再発防止などの措置を実施するよう勧告、公表を行います。
(3) 罰金
荷主が、発注書面を明示・交付する義務、取引記録に関する書面の作成・保存義務を守らなかった場合は、違反行為をした者だけでなく、会社も「50万円以下の罰金」に処せられます。また、書面調査において報告を行わずもしくは虚偽の報告をした場合、公正取引委員会や中小企業庁の職員による立入検査を拒みもしくは妨害した場合にも罰金に処せられます。
6.弁護士に依頼するメリット
以上のとおり、下請法の改正により、荷主と運送事業主との間での取引についても下請法が適用されるようになります。
また、荷主の禁止行為も新たに追加されるため、従前の運用のままでは、下請法違反となり、罰金等が課されるリスクがあります。このようなリスクを避けるためにも、専門家である弁護士の助言を受けることが重要です。
下請法の改正にどのように対応すればいいか分からないなど、お悩みがある事業者の方は、まずは弁護士にご相談ください。
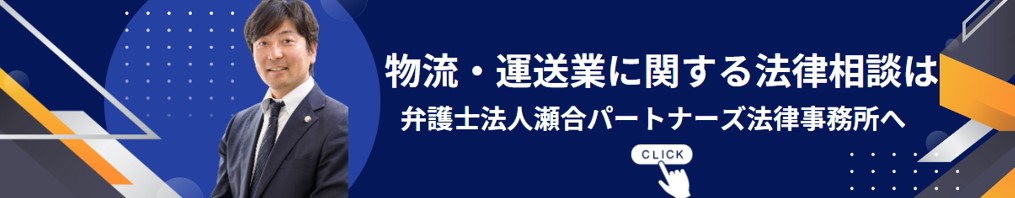
Last Updated on 2025年5月15日 by segou-partners-logistic